令和7年度第1回天理市議会定例会 施政方針

◆ はじめに(総論)
我が国の少子化が加速化しています。全国の令和6年の日本人の年間出生者数は、令和4年に80万人以下に低下してから僅か2年で70万人を下回り、推計68.5万人で過去最少を更新しました。20年前の平成16年は、年間110万人が誕生していました。現在でも、生産年齢人口の減少により、様々な業界で人出不足が課題となっているところ、今後ますます深刻化することは避けられません。
政府は、「地方創生2.0」を打ち出しました。これについて、全国市長会における関係省庁幹部の説明から示唆に富む説明がありました。
「従来の地方創生との違いは何か。『まち・ひと・しごと創生法』が施行された10年前には、地方創生によって人口が徐々に増加に転じるとの淡い期待もあった。しかし現実には、自治体毎に無償化や補助金の給付など子育て世代の負担軽減等に努めてきたけれども、我が国全体の人口減少は止まらず、自治体間で人口が水平にスライドするだけだった。地方創生2.0は、人口は当面減少するとの事態を正面から受け止めた上で、人口規模が縮小しても経済成長し、社会を機能させる適応策を講じていくことを目指している。」
これは将に、1年前に私が議場で述べた令和6年度の施政方針において、本市が「人口減少社会適応都市宣言」を行った認識と合致しています。
本市の昨年の出生者数も、341名に留まり過去最少です。人口割合で見れば、全国平均並みですが、私が就任した平成25年の555人から約4割も減少しています。10年前に、学校に係る施策を検討する際には、1学年当たり概ね600人を前提にしていました。こどもが半減する事態は、既に本市においても現実のものとなっているのです。
こうした中で、学校をはじめ市内公共施設の老朽化が進んでいます。この12年間の必死のやりくりの結果、今年度末の財政調整基金の残高は35億円の見込みとなり、一時の3倍まで積戻すことができました。将来負担比率も平成25年度の101.9%から、24.8%まで改善しています。しかし、これから10年~20年の内に耐用年数を迎える全ての施設を更新することは、不可能です。
施設を合理化、効率化しながら、市民サービスを守り、かつ充実させていくことができるか。全国の地方自治体が直面する課題です。学校についても、統廃合を積極的に進めている自治体もあります。ここに、100%の正解も100%の間違いもありません。地方ごとの事情に応じて、市議会、市民と共により良い選択に向けた合意形成を行うことが大切だと考えます。
本市は、「人口減少社会適応都市宣言」を打ち出す中で、天理市における重層的な地域コミュニティが、小学校区を核として長年育まれてきたことを重視し、学校は小規模であっても敢えて統廃合を選ばず、地域の支え合いの拠点として充実させていく方針を示しました。学校は「地域の宝」だ、という本市のメッセージは、報道でも注目されています。学校教育と、生涯教育、社会教育を「学校三部制」として連携させ、地域みんなでこども達を育み、そしてこども達と一緒に、地域の絆を育む、天理らしい「共育」を基本理念とします。
老朽化調査の結果、先ず山の辺小学校と柳本小学校が、建て替えを要する状態であることが判明しました。山の辺小学校は東部・祝徳公民館と、柳本小学校は柳本公民館と、それぞれ統合・複合化した整備を行います。令和7年度は、民間の知見を活用するため基本構想の提案募集を行い、こども達や保護者、地元の参加を得ながら、設計施工に向けたプランを決定します。学校三部制に基づく新たな学校のモデルとして、令和8年度から建設にかかり、令和10年夏の新校舎移転を目途に、両校を整備する方針です。また、災害時には、学校は「救える命を救う」ための避難所になります。阪神淡路大震災から30年となる今年、防災の視点も含めて計画を練り、平時から共助と公助の絆を育む拠点としていきます。
学校のハード整備にいくら予算を投じたところで、こども達が本当に学びの楽しさを実感できる「魂」が宿っていなければ、意味がありません。教員不足が全国的に課題となっています。本市は、先生方がこども達に向き合い、「第一部」の授業の充実に集中できる環境を創ることを重視しています。社会経済的な格差が広がる中、公教育のあり方と意義を改めて見直す必要があります。塾や習い事が多様化する一方で、体験機会がほとんどない児童生徒もいます。学校は、もはや独占的な教育リソースではありません。公教育が「形式平等」を重んじたところで、実質的な不平等は広がっています。
情報通信技術が急速に発展し、地球環境の激変など、不確実性が増した社会では、正解がない新しい価値創造やイノベーションを創出する力が求められます。与えられた定型的な課題に、予めインプットされた知識に基づいて、正解にたどり着く技能を身につけることは、まったく不要になった訳ではありませんが、もはや十分ではありません。こども達は、多くの職業が、人工知能に置き換えられていくであろう将来を生きることになります。知識を正確に記憶し、ルールや規則を忠実に守り、個人を所属する集団の一員へと育成する「集団指導」から、教育をアップデートすることが不可欠です。この点は、2027年の学習指導要領改訂を目指す文部科学省関係者との議論を通じて、政府においても強く意識されていると認識しています。
そこで本市では、総合教育会議での議論を経て、来年度から5年間を対象にした新教育大綱(案)を策定し、現在パブリックコメントに諮っています。大綱案では、「集団指導」から「ひとりひとりの『しなやかさ』を育む『共育』」への転換をテーマに掲げました。社会が必要とする人材を「製造」するのではなく、次の時代を生きる人間が、幸せに生きていくための力を共に育むことを目指しています。
新教育大綱では、自尊感情やコミュニケーション能力、計画性・楽観性の育成に加えて、「SOSを出せる力、サポートを受けられる力」の育成を4要素の一つとして重視しました。「すぐに弱音を吐くな」という発想や、内面の苦しさを慮らず「励ます」ことによって、「本当は苦しい」と素直に言い出せない風潮が日本社会に残っていないでしょうか。不登校が過去最多となり、若者の第一の死因が自殺という深刻な状況に対して、SOSを出してサポートを受けられる力を育むことは不可欠です。
本年度から開設した「ほっとステーション」は200を超える家庭から、2月末時点で延べ400件を超える相談をいただきました。学校・保育現場を訪問して一緒に課題解決を図るケースも231件に上っています。こども達も、ご家庭も、先生方自身も、それぞれに不安を抱え込んでしまう中で、「SOSを出せる力、サポートを受けられる力」が十分に発揮できていないケースが多くみられます。経験豊富な校園長OBOGと、心理士などがチームとなり、専門的な視点を交えて児童生徒と保護者の不安や生きづらさの原因を「見立て」、周囲とのかけ違いを癒し、安心を育むために取り組んでいます。
文部科学省と財務省は、教育現場の根本的な働き方改革を求め、特に残業時間を月30時間以内に抑えなければ、教員の人材不足は解消しないとの危機感を示しています。自治体に、残業時間管理の計画策定も義務づけられる見込みです。
ほっとステーションの稼働により、まだ全てではありませんが、連携が進んでいる学校では残業時間は大幅に短縮され30時間以内に収まるようになりました。当該学校の教職員からは、体力的精神的な余裕が生まれたとの声も聞けるようになっています。「見立て」をしっかりと行い、チームで対応することによって、教職員だけが課題を抱え込むことを軽減し、今年度の退職者数と休職者数は、過去5年間と比較して激減しました。
飽和状態にある教育現場において、まず教職員がこども達に向き合うための「余白」を生み出さなければなりません。このメッセージは全国の地方議会や教育関係者に徐々に届きつつあります。今年度は沖縄から北海道まで、全国から25件の視察をほっとステーションに迎えました。また、文科省だけでなく、こども家庭庁、財務省や総務省、国会関係者もほっとステーションに注目し、2月には衆議院会館で事例報告も行いました。
生み出した「余白」をどこに向けるべきか。今、文科省も教職員が真にやるべきことと、他部署に事務を委ねることの分類に力を注いでいます。教育大綱案では、「第一部」の授業を、こどもまんなかの視点に立って再構築し、充実させていくことこそ、教職員しかできない、本当に教職員が全力を尽くすべきこととして掲げました。ICT端末の活用に加えて、生徒に優劣の「レッテル」を貼ることなく、習熟度に応じた授業を工夫することは、大きなポイントです。例えば、塾で習っている児童生徒も、得意分野を伸ばしたり、興味のある内容を「探求」できる授業を創る一方で、自分のペースに合わせて復習を中心にした授業も準備し、こども達が選択できるようにすることは、大きなチャレンジですが、真剣に考える必要があります。
そこで、令和7年度中に各小中学校から有志の教員を募り、様々な習熟度の子どもたちが興味を持ち、学ぶ楽しさを感じられる新しい授業を考えるためのプロジェクトチームを立ち上げます。
クラス内で特定の児童生徒が騒いでしまい、授業運営が厳しくなっているケースも稀ではありません。相当の割合で、その発端には「一斉授業についていけない」という学習面での悩みがあります。不登校対策では、本市はゆうフレンドや、適応指導教室などを長年実施してきました。しかし、学校で過ごす時間のほとんどは授業です。授業が自分にとって「苦しい」ものであれば、学校が安心できる居場所になることはありません。普通学級と特別支援学級に二分するだけでは、対応しきれない状況が生まれています。教職員の側も、カリキュラムの全てを「こなさなければならない」という義務感を少し緩めて、こども達の実態やニーズに応じて柔軟に対応することが不可欠です。ほっとステーションは、教職員が、これまで本当に取り組みたかったけれども、時間的に精神的余裕がなかった、という状況を改善していきます。
同様に、行事や様々なルールはこども達に何を育むためにあるのか、クラブ活動の地域移行は、単に負担軽減のためだけではなく、こども達の人間的な成長をどう育んでいくのか、「こどもまんなか」の視点から問い直します。
人権教育のアップデートも極めて重要です。SNSの普及により、匿名性と拡散性が急速に高まり、誹謗中傷や根拠なきデマは、人の心を傷つけるに留まらず、時に命を奪うほどに狂暴化しています。本市は、「天理市部落差別の解消の推進に関する条例」を制定しましたが、残念なことに法務局に削除要請をせざるを得ない事案も稀ではありません。
「差別は倫理的に正しくない」「人の気持ちを思いやろう」というだけでは十分な対策とは言えません。自分が抱える不安や劣等感、周囲から受ける不条理への怒りなどを、他者に転嫁して攻撃する人を生まないための孤独孤立対策、「SOSを出せる力」の育成が重要です。地域の様々な人とこども達が触れ合い交流することは、この点でも重要と考えています。加えて、こども達の情報リテラシーを高めなければなりません。SNSでは、利用者の閲覧履歴から似通った情報が優先的に表示されるため、偏った情報に関心を示した人が、その価値観のバブルの中に孤立してしまう状態「フィルターバブル」に陥る危険性があります。所謂「闇バイト」のリスクなどに加えて、こうした情報の偏りについても適切に学習することが、これからの時代を生きるうえで不可欠です。
ヘイトクライムに関する英国の専門家は、「憎悪を煽る情報は、誤報であると認識する」「自分と異なる他者と接触する機会を避けない」「私たち全員が、憎悪行為の第一対象者になり、見て見ぬふりをしない」などをヘイトクライム防止の条件に掲げています。これらは、こども達だけでなく、大人の私たちも「共生社会」を目指す上で身に着けるべき素養であり、人権教育のアップデートに当たって重視して参ります。
人口減少社会への適用を目指す上で、今回の施政方針では、先ず誰もが安心でき、自分らしくいられるための学校づくり、これから本市が目指す教育について冒頭でお話ししました。格差の広がりや物価高騰を含め、市民生活に影響する課題は多様化・複雑化しています。こども達の教育だけでなく、福祉の分野においても縦割りの対応では全く追いつかない状況であり、重層的な支援体制の構築を急いで参ります。
また、人口減少にしなやかに適用していくためには、町の活力を高める努力もしていかなければなりません。天理大学や民間団体、企業との連携を深め、歴史、文化芸術、スポーツなどの天理の「宝」をこれまで以上に活かすことも大切です。暮らしと産業を支える市役所業務もまた、限られた人員と予算、時間という前提の中、できるだけきめ細かい市民サービスを、やりがいを持って進めるため、デジタル化を軸とした転換が求められます。「人口減少社会適応都市」天理で暮らす豊かさと安心、幸福を「共に育む」をコンセプトとして、令和7年度予算を編成しました。
(令和7年度天理市一般会計予算(案)の概要)
議案第3号、令和7年度天理市一般会計予算(案)についてご説明申し上げます。一般会計の予算額は、歳入歳出とも284億7千万円、前年度比で41億4千万円、12.7%の減額となりました。ただし、前年度当初予算は、やまとecoクリーンセンターや櫟本北こども園等の大型建設事業費が重なり過去最大の予算規模となった特殊事情がありましたので、令和7年度は、昨年度に次ぐ過去2番目の予算規模です。
◆歳入
歳入からご説明します。
市税のうち、個人市民税は、賃金指数の上昇がみられることなどにより、前年度当初予算より1億3,800万円の増額を見込んでいます。固定資産税についても、家屋・償却資産の増加により、1億900万円の増額となります。市税総額は、80億2,700万円、前年度比3億300万円、3.9%の増収となる見込みです。
地方消費税交付金は、前年度比1億260万円、7.2%の増収の15億3,600万円となる見込みです。地方交付税は、65億1,800万円となり、前年度比3億1,400万円、5.1%の増収を見込む一方、臨時財政対策債は、前年度比5,700万円の皆減となります。
国庫支出金は、児童手当負担金や障害自立支援給付費負担金のほか、デジタル基盤改革支援補助金等が増加するため、前年度比7億100万円、16.8%の増の48億7,000万円となる見込みです。
市債は、旧クリーンセンターの解体や小・中学校体育館の空調機器設置にかかる整備事業債等が増加します。一方で、やまとecoクリーンセンター・天理市清掃管理事務所、櫟本北こども園等の建設が完了したことで、市債全体では前年度と比較し60億8,200万円の減少となる見込みです。
道路等の整備や学校関連施設などの公共工事は、引き続き市民の命と安全・安心を確保するために緊急性のある優先すべきものを十分精査し、国の経済対策等を踏まえ、国庫補助金の活用や償還時に地方交付税措置等のある有利な起債の利用に努めます。
令和7年度末の一般会計における市債残高は、264億6,000万円となり、過去に借り入れた市債の償還元金を差し引きすると、前年度に比べて10億6,100万円減少する見込みです。
令和7年度の市債元利償還金は、臨時財政対策債を含め約22.1億円となりますが、このうち5割程度は普通地方交付税の基準財政需要額として算定されています。
天理教からの寄附金は、前年度と同額の2億円を見込んでいます。
基金からの取り崩し額は、減債基金が1億2,900万円、公共施設整備基金が8,100万円で財政調整基金の取り崩し額は、前年度に比べて3.1億円減の7.2億円です。令和6年度の決算時には、約5億円の積み増しがあるものと想定され、令和7年度末の財政調整基金残高は約34億円を確保できるものと見込んでいます。
ただし、令和7年以降も4億~7億円程度の財源不足が毎年続くと見込まれます。今後、老朽化する公共施設の整備には公債費の増加を含め多額の費用が必要です。懸念される震災等にも備え、機動的に動くためには、一定規模の基金残高を確保しておく視点も必須です。平成終盤の基金残高と比較すれば、3倍程度の額を一時的に積み上げているものの、油断は禁物です。将来、予算編成が困難となる事態を避けるためには、令和元年度から取組んでいる財政構造改革を一層深め、スリムかつ柔軟な行政サービスを追求しなければなりません。
◆歳出
次に、歳出について申し上げます。
目的別の歳出では、歳出全体の45.2%を占める民生費は、128億7,200万円、前年度比1億7,200万円、1.4%の増加です。内容としては、児童手当、こどものための教育・保育給付費負担金、障害福祉サービス介護給付費が増加した一方、櫟本北こども園建設工事費分は皆減となっています。
総務費は35億7,600万円、天理市総合体育館LED化事業や参議院議員通常選挙費及び市長選挙費、国勢調査事業費等の増加により、前年度比5億1,000万円、16.6%の増となりました。
教育費は30億9,100万円、GIGAスクール1人1台端末更新事業や各小中学校の屋内運動場等空調機器設置事業の増加により、前年度比7億5,500万円、32.3%の増となりました。
衛生費は26億7,000万円、旧クリーンセンターの解体工事は増額となる一方、山辺・県北西部広域環境衛生組合分担金は建設工事の完了により減少、天理市清掃管理事務所建設工事費が皆減し、前年度比56億6,300万円、68.0%の減となりました。
予算規模が過去2番目に多い284億7,000万円となった要因として、火葬場や小中学校の老朽化に伴う施設改修費、旧クリーンセンター解体費に加え、近年の地球温暖化による異常気象に対応するための、幼稚園遊戯室や小中学校体育館等への空調機器設置費などが増額となっています。また、障害(児)福祉サービス給付費や児童手当等の扶助費、民間保育所等の負担金なども国の政策により増額となっています。
以上が歳入歳出予算の全体像です。これより、令和7年度予算の編成方針で掲げました5つの柱に沿って、重点施策について順次ご説明致します。
Ⅰ.地域と共に、一人ひとりの豊かな未来を育む「教育・子育て」の充実
第一の柱は、地域と共に、一人ひとりの豊かな未来を育む「教育・子育て」の充実です。
学校三部制の推進のため、区長会をはじめ地域団体又は文化、芸術、スポーツ、ボランティア等の地域活動で実績のある団体が施設を使用できるよう、「学校三部制に係る教室等の活用に関する規則」を制定しました。施設管理については、学校長の責任は「第一部」の授業等で利活用する範囲に限定し、第一部から第三部までを通じて全般の責任は教育委員会が受け持つことを明確にしました。
令和6年度は11団体が、学校施設を活用した社会教育・生涯教育活動を「第三部」として行いました。「第一部」の授業でも、21団体、書道や俳句、郷土史など公民館の教室やクラブのメンバーが指導に加わり、交流を通じた学びが進みました。ペットボトルキャップ、インクカートリッジ等を集めるイチカステーションの取組により、こどもから高齢者までが交流を通してSDGsについて学ぶ機会も広がっています。中学校では、地域包括支援センターとの連携により、高齢者の生活面での困難を実体験する講義を行っています。文科省及び厚労省の共同で、こども達の認知症への理解促進を図るよう通達が出ています。学校三部制の下で福祉を学び、地域の高齢者と触れ合う機会を創ることは、人格形成の時期にある生徒にとって大きな意義があります。
令和7年度は、学校図書館の活用も進めます。櫟本小学校では、就学前児童に図書室を開放する「みんなのとしょかん」を定期的に行い、市立図書館から児童書の貸し出しもおこなってきました。「第二部」の学童保育にとっても、図書館は重要な活動の場となっています。一方で、多くの学校図書室は、蔵書や備品が老朽化し、利用率が低下しています。柳本小学校をモデルとして、蔵書・備品の更新やデジタル化、読書推進のためのお話し会の開催などを行い、地域の大人の利用も視野に入れ、読書を通じた多世代の居場所づくりを行います。
安全面の対策として、令和6年度は監視カメラや警察と連動した通報システムを導入し、地域の利用者のためにリモート式の電子錠を設置しました。信頼できる地域の大人の目が、校内や地域に増えることで犯罪抑止力になると考えており、「閉ざされた校内」から「信頼できる大人の目に守られる校内」へシフトさせていきます。
災害対策では、学校は大規模な避難が必要となった場合に、「救える命を救う」ための共同生活の場になります。避難所開設を迅速に進めるため、学校の鍵を消防団の各器具庫に設置しました。また市民の皆さんが、「こどもが卒業してから何十年も学校にいっていない」「近所の人にほとんど顔なじみがいない」という状態では、避難所での共助を立ち上げることは困難です。毎年、校区毎に実施している避難訓練では、学校教室を活用した避難生活の体験を盛り込んでいます。学校三部制は、平時から支え合う地域の絆を、学校を拠点に育む取組みでもあります。
「学校三部制」を施設面で支える取組みとして、本市は空調整備を段階的に進めてきました。避難所としても活用することから、防災上も重要な意義があります。令和6年度までに、普通教室と主たる特別教室への設置を完了しました。この春休み期間中、給食調理室の空調整備を行います。異常気象が常態化し、猛暑日が急増しています。令和7年度の夏休み期間に、屋内運動場への整備を目指します。
学校の第一の目的は、もちろんこども達の学習、「第一部」にあります。地域の利活用によって、「第一部」が制限されることがあってはなりません。しかし、今課題となっているのは、核家族化の中で、こども達が自分の家族と教職員以外の大人と交流する機会が減っていること、それにより、コミュニケーション能力を育成する機会が失われていること、家庭の状況により体験機会などに格差が広がっていることです。
学校三部制を通じた地域との交流の中で、こども達には他者を思いやる気持ちや、自分の役割を果たし、それが褒められる成功体験による自尊感情、郷土への愛を育んでくれることを期待しています。また、高齢者を含む地域の皆さまとっても、生き甲斐を感じられる居場所をつくる意義があります。心身の健康を維持する上で大きな効果があることが、櫟本小学校の「夢応援プロジェクト」など先行した事例が示しています。人口減少社会において、改めて学校は地域みんなの「宝物」であることを、天理から示して参ります。
また、第一部を充実させるために、令和7年度は小中学校合わせて約4,500台のGIGAスクール端末を更新します。奈良県校務支援システムの更新に対応して、本市のネットワークの改修も実施します。デジタル化は手段であって、目的ではありません。デジタル教材の積極活用なども重要ですが、GIGAスクールの大きな目的は、黒板への「板書」主体の一斉授業から、児童生徒の学習状況に合わせて、ひとりひとりにとっての最適化を図ることです。継続的に学習力の推移についてデータを蓄積し、教職員の指導に活かすことも期待されます。新教育大綱案に基づき、天理らしい学習のデジタル化を図ります。
教職員を支え「働き方改革」を進めつつ、児童生徒の学習サポートを行うため、教員業務支援員や、児童生徒学習支援員の配置を継続します。
合わせて令和7年度は、不登校から復帰段階にある児童生徒や、不登校の傾向がみられる児童生徒が、学校内において、自分に合ったペースで学習・生活ができる環境として「校内教育支援センター」の設置を進めます。授業中に周囲との折り合いを付けることが難しいこども達が、一時的に落ち着くための「シェルター」も重要です。今年度から実験的に複数校でシェルターの運用を開始しており、令和7年度は必要に応じて、できるだけ配置を進めます。これまで市単独予算で配置していた人権教育推進講師は、「こども人権まんなか教員」「シニアほっとアドバイザー」に名称と役割を変えます。ほっとステーションが司令塔となり、学校と連携しながら、これらの講師を機動的に派遣し、校内教育支援センターやシェルターの運営を行う方針です。
また、天理市立北中学校夜間学級を不登校対策の点からアップデートし、「フリースクール化」します。天理の「夜中」は、国籍や年齢を超えて、読み書きなどの学習を通じて人間の尊厳を回復する極めて重要な役割を果たしてきました。戦中戦後期の生徒が概ね卒業を迎えた中、結婚や就労のため来日した生徒など多様化しています。令和7年度から、現役の中学生の受け入れも本格化させ、一定の学習効果を学校長が確認した場合には、「出席扱い」とし、居場所の選択肢を増やします。
新教育大綱では、不登校は、「学校に来なくなること」が問題なのではなく、「学校が、こどもにとって安心できる居場所でなくなった」ことが問題なのだと捉えています。定時に学校に無理にでも来させる「圧力」を加えるだけでは、こどもの心はより深刻なダメージを負ってしまいます。自室や家の他に、「どこかに安心できる居場所がある」「家族以外の誰かと繋がっていられる」ことを先ず優先します。その上で、徐々に学校に通う他のこどもと同じリズムに戻っていけば良いですし、仮にそれが難しくとも、将来社会と繋がっていける力を無理なく育んでいくことが大切です。
ゆうフレンド派遣は、こうした視点から捉え直します。また、適応指導教室「いちょうの木」は、「適応を指導する」という視点と姿勢を改める必要があり、(仮称)「ほっとスクール 昼の部」と変更します。これに合わせて、現役中学生を受け入れる夜中事業は、「ほっとスクール 夜の部」とします。
不登校の原因は多様かつ複合的なものです。家族の介護や家事の負担のために、こどもが通学を含む日常生活を送ることが困難な「ヤングケアラー」対策として、支援員が家事支援や育児支援を行う対策を令和6年度から実施しています。令和7年度は、ほっとステーションを軸として、福祉と教育の連携を深めていきます。
いじめ対策では、最近でも泉南市でいじめを訴えていた13歳の生徒が自ら命を絶つという痛ましい事件が発生しました。他方で、「ほっとステーション」の対応から、多くのいじめ事案では、「加害者」「被害者」を簡単に二分できる訳ではなく、双方の児童生徒の苦悩やいきづらさに寄り添い、心を解きほぐしてくことが大切だと認識しています。
他者を傷つける行為に対して、「自分も嫌な思いをした」などの「動機」には共感しつつ、「選択」が誤っていたことを教え諭し、繰り返さない教育を行うことが重要です。また、SNSでのやり取りを含めて、「事実」と「想像」を混同して、自分が過度に嫌われている、疎外されていると感じているケースや、周辺の騒がしさに過敏に反応してしまう場合には、周囲との掛け違いやすれ違いと向き合い、時に受け流し、折り合いをつけていく力を育む必要があります。
もちろん、いじめの深刻化防止のため、迅速に介入すべき事態には主体的に判断して対応し、身体の安全を緊急に確保すべき時には、弁護士を含めて直ちに阻止することを躊躇しません。いじめ対策についても学校だけが抱え込み、教職員が萎縮している間に深刻になる事態を避けるため、ほっとステーションに、個別のいじめ事案へより直接的な対応や加害児童生徒への指導・支援を担う「いじめマイスター」を設置し、より一層問題解決に向けての体制を強化します。さらに、児童福祉分野とも連携した地域におけるいじめ防止対策の体制を構築します。
働き方改革の一環として、政府は中学校の部活動地域移行を進めており、奈良県では令和8年度から本格実施される予定です。本市では、部活動は学校三部制の「第二部」と位置づけ、第一部と区分します。部活動の指導に引き続き関わることを希望する教職員については、「副業」と定義し、平日勤務時間中は職務免除、勤務時間外や休日には副業としての手当を別途支給します。現在、教職員の希望調査を行っており、教職員では埋められないクラブ活動の種目や時間帯を早急に整理します。その上で、スポーツや文化芸術活動など市内団体と協議の上、貢献いただける地域人材を「有償ボランティア」として募集し、令和7年度は可能な部活動から試験運用を広げていきます。
異なる国籍、民族、宗教の人達との交流を行い、互いに認め敬意を払い合うことは、「共生社会」に向けて決めて重要です。姉妹都市・瑞山市との中学生交流は、平川商事のご協賛や天理大学の協力を得て継続します。また、天理大学・JICAと本市の三者協定に基づき、天理大学柔道部の関係者が、エジプト柔道チームの育成に当たっています。海外協力隊員として派遣された学生によるエジプト講座や、カイロの日本式学校との交流を引き続き実施予定です。
本市の「ほっとステーション」は、就学児童・生徒だけでなく、就学前の幼児教育・保育を合わせて運用していることが大きな特徴の一つです。児童生徒の生きづらさや保護者の不安感は、就学前から継続しているケースも多く、教育委員会と児童福祉の垣根を越えた対応が必要です。新教育大綱は、0歳児から15歳の義務教育修了まで、こども達の成長を連続した流れとして捉え、一体的に作成しました。「愛着形成」の観点から、ほっとステーションによる学校支援において、園長所長経験者が教育現場に入る機会も増えています。
幼保の体制整備では、令和7年4月より北保育所と櫟本幼稚園を統合し、「櫟本北こども園」を開園します。近年の幼保一元化や民間保育所の誘致により、本市では、「盆地のいずれかの園所には受け入れ枠がある」という意味で、令和5年度より待機児童は解消しています。令和5年度には、市立メディカルセンターと連携し、病児病後児保育サービスも開始しました。令和7年度は施設改善のため、園所のトイレ洋式化、空調の更新、幼稚園遊戯室の空調整備などを実施します。
他方で、幼稚園の新規入園者数は減少傾向が続き、一ケタの園も発生しています。できるだけ身近な地域で就学前の受け入れを持続させていくためには、幼保再編の更なる推進が必要です。朝和幼稚園と柳本幼稚園の一体運用を進めるほか、二階堂幼稚園と嘉幡保育所の統合によるこども園化に向け準備を行います。
乳幼児期からの愛着形成、その前提となる家族の孤独孤立対策などは、切れ目のない福祉として捉えていかなければなりません。令和7年度は、教育大綱と連動させながら、「天理市こども計画」を策定し、こどもの人格・個性の尊重及び権利の保障、こどもの安心安全な居場所の確保、こどもの意見表明や社会参画の機会の保障等、こどもの持つあらゆる権利・機会について、「こどもまんなか社会」の実現に向けた方向性を示します。
本市は、令和6年度より「はぐ~る」を拠点として、「こども家庭センター」を運営しています。母子保健と児童福祉の一体的な運営を通じ、妊産婦及び乳幼児の健康の保持・増進に関する支援、こどもと子育て家庭の福祉に関する支援を包括的かつ伴走的に提供することが可能となりました。家庭支援事業を含め、様々な支援メニューを整理するための「サポートプラン」の作成を引き続き行います。
少子化対策として、一般不妊治療にかかる費用助成を行ってきた他、令和4年から生殖補助医療助成も追加してきました。令和7年度から県補助金も創設されることを受け、保険適用回数の超過や年齢超過の方も補助をより受けやすくなるよう、助成を拡充します。
出産後間もない時期の産婦は精神的に不安定になりやすく、孤独孤立の解消は虐待防止の点からも重要です。本市では、精神ケアや休養の確保を目的に、助産院でのショートステイや、デイサービスの利用促進を行っている他、ドゥーラによる「こんにちは赤ちゃん訪問」や育児家事支援を実施しています。令和6年度は、2名のドゥーラを新たに養成し、令和7年度より4名の体制でよりきめ細かい伴走型支援を行います。子育ての悩みや不安を抱える保護者に対する「イライラしない子育て講座」を実施する他、新たに産婦検診費用の助成を開始します。また、市による「1か月児」健康診査を開始し、児童の成長発達、疾病の早期発見、育児不安および産後うつの予防を図ります。
こども達や子育て家庭の孤独孤立対策では、支援を受けたい方と支援したい方をマッチングする「ファミリー・サポート・センター」事業を継続し、「はぐ~る」におけるメールやLINEでの育児相談を充実させていきます。こどもの居場所支援では、令和6年度から旧御経野老人憩いの家を、(一社)天理文化の会と協働して実施しています。学習支援、食支援、心理士による心の支援を一体的に実施し、地域の方との交流も重視しています。隣接する御経野児童館も老朽化が進んでおり、令和7年度は、民間活力の活用も視野に入れながら、居場所づくりの充実を図ります。
市内の「こども食堂」は、コロナ禍の試練を経て、配食の継続や会食の再開など、それぞれの状況に応じて発展してきています。地元消費を「支え合い」に繫げる「イチカプラス」事業も定着しつつあり、本市が「SDGs未来都市」に認定される重要な要素になりました。令和7年からの新たな取組みとして、2月にセブン-イレブン・ジャパンと「フードドライブの実施に関する協定」を締結し、市内5店舗で回収された余剰食品を、9つのこども食堂に提供する枠組みも始まりました。「フードバンク天理」による食品回収ボックスの設置箇所も10カ所に増え、令和6年度は約760kgの食品をこども食堂に提供することができました。「おてらおやつクラブ」との連携によるひとり親家庭の支援も着実に根付き、天理ならではのお裾分けとして市内産のお米やジャムの同梱も進んでいます。令和7年から、図書館が3歳以下の児童がいる家庭に絵本をお届けする「絵本配達便」も開始しました。令和7年度も引き続き、様々な団体と連携し、支え合いの輪を広げて参ります。
少子化の背景として、晩婚化や未婚化が挙げられることもあります。しかし、人生のあり方や幸せについての価値観が多様化している時代に、「社会のために、結婚すべき」「社会のために産んで」と聞こえてしまうと、説得力がないどころか、「生きづらさ」を生んでしまうだけです。
そこで本市は「少子化・孤独孤立等対策応援事業」を令和4年から実施しています。妊娠・出産期から切れ目のない福祉を目指して取組んできた中、その前の家族になっていくところまで根本に立ち返った事業です。性別を問わず大切な人と出会い、パートナーや家族となっていくことを、行政ではなく、ボランティア「ハローパートナーシップ(通称:ハロパト)・メンター」が主体となり、同じ市民の視点と立場から応援します。現在22名のメンター活動し、支援下さる市内企業・事業所も84団体に広がりました。パートナーと出会うことを希望しているけれども、不安や孤独も抱えている人達が、自分なりの幸せを形づくっていく道筋を、伴走し続けます。
天理大学自治会と共同して行った調査では、天大生の約8割は将来的に結婚を希望すると回答し、全国平均よりも高い数値でした。
ハロパトの支援を通じて、結婚につながった実績も生まれており、同種の事業を行う他の自治体との間でのカップル成立も見られます。令和7年度は、協力事業所とも連携し、結婚と就労を一体的に捉えたサポートも模索していきます。ハロパトは令和7年度中の法人化を目指します。
Ⅱ.誰もが地域で安心して健やかに暮らせる「福祉」の充実
第二の柱は、誰もが地域で安心して健やかに暮らせる「福祉」の充実です。
市民が抱える課題は、多様化・複合化しており、従来の縦割りの支援体制では対応しきれません。
本市では、令和5年度から7年度の3カ年で、市役所及び社会福祉協議会を含む庁外関係機関が重層的支援に対応できるよう体制整備を行ってきました。令和8年度から本格始動できるよう、横断的な体制を「てんりシフト」と命名し、様々な支援をマネジメントするコーディネーターを育成して参ります。
令和7年度は「天理市地域福祉計画・地域福祉活動計画」の最終年度に当たり、年度中に次の5年間を対象とする次期計画を策定します。「重層的支援体制整備事業実施計画」「認知症施策推進計画」「再犯防止推進計画」「成年後見制度利用促進計画」、そして社会福祉協議会が策定する「地域福祉活動計画」も一体的に策定する方針です。
地域福祉の中核的役割を果たす民生委員は、近年重要性が高まる一方で、負担の増加や担い手不足が課題となっています。令和7年度は、民生委員の負担軽減や担い手不足の解消を図るため、活動の補佐・協力を行う「民生委員協力員制度」を導入します。天理市が民生委員協力員を委嘱し、見守り活動や資料等の配付、イベントなど地域福祉活動への参加・協力などをお願いします。
女性が抱える問題の支援では、令和6年末に「家庭児童相談・女性相談支援室」を設置し、「女性相談支援員」を配置しました。これまで奈良県窓口への相談が初動対応でしたが、本市がワンストップで受けつけることが可能となりました。DVや性被害など、子育て家庭以外にも悩みを抱えられる女性は少なくなく、早期からの切れ目のない支援を図ります。
令和6年度から、ガン患者を対象に、医療用ウイッグや補正具等の購入費補助を開始しました。治療による脱毛や乳房切除などの外見(アピアランス)の変化による心理的負担のため、他者とのかかわりを避けることや、自分らしく生きられないなどの悩みを軽減することを目的とします。令和7年度も事業を継続し、制度の啓発を進めます。
高齢者の生活支援では、本市は住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるまちづくりを進めてきました。市内4圏域に生活支援コーディネーターを配置し、高齢者に伴う課題の掘り起こしとその解決に努めています。生活支援コーディネーターは、制度上介護サービスでは対応不可な「ちょっとした困りごと」などを助けてくれる有償ボランティア「天理市生活支援サポーター(愛称:てんさぽ)」を養成しています。一緒に散歩をすることや、お話をするなども重要な支援であり、天理大学生など若い世代のボランティアが活躍しています。年間のマッチング件数は100件を超えており、令和7年度以降はボランティアの育成と一層の活用促進を図ります。
介護事業では、小学校区レベルで小規模多機能型居宅介護施設を整備し、地域密着型の支援を進めてきました。加えて、市内の種苗企業「大和農園」が農福連携を目指して新たな社会福祉法人を立ち上げ、本市では6つ目となる特別養護老人ホームの新規整備を予定しています。
認知症対策では、認知症当事者や家族が集う「認知症カフェ」、家族が相談できる「オレンジサロン」、疑いのある方の早期診断・対応につなげるための「認知症ケアパス」の普及、世界アルツハイマー月間イベントの実施など、正しい理解の下に、認知症になっても安心して暮らし続けられる地域づくりを目指して取組んでいます。行方不明者を捜索するための「みまもりあいアプリ」では、若年性認知症の当事者や医療関係者がラジオ機能を活用して啓発に取組んでいます。
活脳教室は令和6年度までに300名以上が参加され、約9割の参加者が認知機能を維持・改善されています。修了後も自主的に継続する「活脳クラブ」が20カ所誕生し、活脳を通じた居場所づくりが進んでいます。
認知症以外でも、市内で介護予防を目指す「通いの場」が118カ所活動中で、生活支援コーディネーターが中心に居場所づくりを進めています。また16名の介護予防リーダーによる「STEP体操」が、メディカルセンター内のまちかど相談室を含めて、拡がっています。図書館における読書バリアフリー事業も進めています。令和7年度も引き続き医療関係者とも連携しながら、各活動の充実を図ります。
高齢化に伴い、免許を返納される方が増加しています。いわゆる「交通弱者」支援として、本市ではならコープと連携し、移動販売を計28カ所で実施しており、令和6年度も延べ4千名を超える利用者がありました。また、移動支援では、令和6年度から奈良トヨタグループ及び交通事業者との連携事業として、AIデマンド交通サービス「チョイソコてんり」の本格運行を開始しました。昨年4月以来、登録者は約3,500名、利用者は本年2月末までに延べ約25,000名に上っています。1ヶ月当たりの予約件数は平均して2千件を超えており、乗り合い促進のための運用改善も昨夏に行いました。予約を取りやすいようにする等、更なる改善は必要と考えており、令和7年度は公共ライドシェアなど他の自治体の例も参考にしながら、補完するサービスの検討も行って参ります。
健康づくりでは、国民健康保険加入者を対象として特定健診に加えて、令和6年度より無料で歯周病検診を受けられる受診券を送付しています。また、ガン検診の受診増進を目的として、1,000ポイント分のイチカポイントを進呈します。子宮がん検診や乳がん検診と骨粗鬆症検診を同時に受診された場合など、費用の減額を行います。
子宮頸がんワクチン接種は、令和6年度がキャッチアップ接種の最終年度でしたが、接種機会を逃した方が多くおられたため、キャッチアップ接種期間中の3年間に1回以上接種している方については、期間終了後も公費で不足回数を接種できるよう1年間の経過措置が設けられました。対象者に個別通知を行うと共に、広報紙等の情報提供を行います。男性に対する子宮頸がんワクチン接種費用の補助は、本市が近畿初で令和6年度に実施しました。引き続き啓発し性別を問わず感染予防を図ります。
また、帯状疱疹ワクチン接種は、令和7年度より予防接種法上の定期接種に位置づけられ、65歳の方が対象者となりますが、令和7年度から5年間の経過措置を設け、100歳までの5歳刻の節目年齢にある方に接種を行います。加えて、100歳以上の方は令和7年度に限り全員が接種対象者となります。
健康推進の分野でも、天理大学医療学部との連携が進んでいます。令和6年度は天理駅団体待合所で「まちの保健室」を実施しました。子宮頸がん予防接種とがん検診を定期的に行うことや、若いころから自分の乳房に関心を持つ習慣「ブレスト・アウェアネス」を生活の中に取り入れることの大切さについて、令和7年度も「まちの保健室」を継続開催し、啓発を行います。
Ⅲ.市民の命と暮らしを守る「安全・安心」のまちづくりの実現
第三の柱は、市民の命と暮らしを守る「安全・安心」のまちづくりの実現です。
昨年は、南海トラフ地震臨時情報「巨大地震注意」が初めて発表されました。政府は「防災・減災、国土強靭化のための5か年加速化対策」を実施してきており、令和7年度には、後続の施策となる「中期実施計画」が早期に実施されるよう、本市も全国の自治体と共に要望活動を繰り返しています。緊急防災減災債なども、この中期実施計画と連動して取り扱われる見込みであり、本市としてはその動向を踏まえつつ、橋梁の長寿命化などを着実に実施していきます。
防災体制では、本市は「救える命を一人でも多く救う」「災害関連死を一人でも少なくする」を目的に掲げ、体制強化に向けて取り組んでいます。本年2月には、丹波市校区を対象に、学校体育館に加え、教室についても配慮が必要な方の居住スペースとした避難所開設初動訓練を実施しました。令和7年度においても今後校区を選定して実施する予定です。政府等からの支援物資を円滑に避難者に分配するため、市内倉庫・運送業6社と「災害時における支援物資輸送拠点に関する協定書」を、3月中に締結予定です。
避難生活を支える物品の充実では、能登半島地震でも課題となったトイレ不足に備え、トイレカーを発注済みであり、年度末までに納入予定です。また政府の令和6年度補正予算では、災害関連死を防ぐため、TKB(トイレ・キッチン・ベッド)等の充実強化が重要視されました。本市もパーティション、シャワーシステム、エアーテント、蓄電池等の整備のため交付金を申請中であり、採択され次第、速やかな調達を目指します。令和7年度は、県と市町村を結び防災行政通信ネットワーク衛星回線についても、再整備を行います。また、「天理市国土強靭化地域計画」に基づき、引き続き防災士の育成などソフト面での体制強化も図ります。
水害対策では、奈良県平成緊急内水対策事業の一環として、浸水常襲地である庵治町の浸水被害を軽減するため、農業用ため池である庵治池の治水整備を進め、令和6年度に工事が完了しました。最大貯水量88,000㎥を貯留が可能となり、寺川への排水口のフラップゲートを県が設置完了次第、10年に1回程度起きる大雨では、浸水が解消される見込みです。県内で初めて農業用ため池を治水専用ため池として利用した新たな取り組み事例として、特定都市河川に指定された大和川流域でも注目されています。
二階堂下ツ道・三の坪周辺では、二階堂校区浸水対策プロジェクト会議や天理市議会水害対策委員会からのご意見を伺いながら県と市が連携して浸水被害の軽減を図る取り組みを進めています。8,000トンの貯留を見込む菰池の治水活用については、県市が連携し、昨年度は降雨時の流入方法及び構造等について地元及び下流域の自治会と協議を重ね、概ね治水活用の整備方針がまとまりつつあります。令和7年度に県による詳細設計を行い、早期の工事着手を目指します。
防災重点農業用ため池は、令和7年度にパトロール21箇所、劣化状況評価16箇所、豪雨耐性評価9箇所、ため池群改修計画策定2箇所を予定しています。防災工事が必要となった場合、工事が完了するまでの間、必要に応じて応急的な防災工事または低水位での管理、損傷個所の保護等を行います。
全国的に中小河川における洪水が多発していることから、水防法が改正され、中小河川における浸水想定区域が加えられました。奈良県においても、令和5年に浸水想定区域が公表されました。令和7年度は、本市の総合防災マップを更新します。
地域防災の要である消防団は、令和6年度に奈良県との共催で、消防署・自衛隊等の協力を得つつ、林野火災訓練を実施しました。竹之内町で発生した火災では、通路が狭く標高もある現場に向けて、消防団のポンプ車が送水し、消防隊の消火活動を支えていただくなど、地元の地理や事情に精通した消防団の大切さを示しました。これらの災害時における活動をより円滑にするため発電機及びバルーン投光器の整備を進めておりますが、令和7年度以降も引き続き災害活動に資する資機材、装備の充実を図ります。加えて、消防団員の退職報奨金について、国の基準に沿って勤続35年以上の支給枠を増設し、消防団員の処遇改善を図ります。
危険空き家への対応では、令和6年度に倒壊が懸念されていた福住町の空き家1軒が、市道を被うように全壊しました。隣接する棟がまだ残っており、特定空き家の指定による代執行も視野に入れながら、危険除去を所有者に促します。柳本町内にも、地元自治会が懸念する集合住宅の空き家が存在しており、代執行の可能性も含めて対応を進めます。今後、老朽化する市内の空き家の全てに、市が代執行で対応することは極めて困難です。資金回収の目処も立たないケースが少なくないと思われます。空き家の傷みがまだ軽度で、利活用できるうちに流通促進に貢献できるよう、「空き家プラットフォーム」の結成を急ぎます。
防犯対策では、自治会等による自主的な防犯カメラ設置に対する補助事業を実施しており、令和7年度は5自治会に補助を見込んでいます。
防犯灯LED化事業では、市内全域において約7,100灯に及ぶLED防犯灯を維持管理しつつ、新たな防犯灯の設置要望に対応しています。令和6年度は、天理教所有の防犯灯の撤去が進められたため、設置要望が大幅に増え、24自治会から申請があった計99灯の設置を行いました。令和7年度も引き続き天理教所有の防犯灯の撤去が行われる予定であり、例年よりも多くの新設要望が見込まれます。自治会と十分協議の上、LED防犯灯の新設募集を行い、LED防犯灯設置の充実を図ります。
また、特殊詐欺被害防止対策として行っている防犯電話購入費補助事業は需要が高まっています。天理市内における令和6年の特殊詐欺被害は12件、被害総額が約5,600万円となっています。被害者の大半は高齢者が占め、今後ますます高齢者人口の割合が増えるなか、特殊詐欺の被害防止は喫緊の課題となっています。昨今、社会問題となっている闇バイトを実行役にした匿名・流動型犯罪グループ(トクリュウ)による強盗事件等でも事前の情報収集として電話をかけてきます。令和7年度は防犯電話購入費補助事業を拡充して行ってまいります。
Ⅳ.活力ある地域社会に向けた「賑わい」の創造
第四の柱は、活力ある地域社会に向けた「賑わい」の創造です。
来年度から5年間を対象とする「第6次天理市総合計画 後期基本計画」の策定に当たって取りまとめた天理市人口ビジョンでは、天理市在住の就労者の内、59.8%は通勤時間が30分以内、25.8%は1時間以内であることが明らかになりました。県内で近距離通勤者の割合がこれほど高いのは、本市の他に五條市のみで、共に京阪神の都市部から離れた支線の沿線です。すなわち、都市部への通勤者は県西部や県外を志向する傾向があり、本市に住み続けるためには、市内乃至近隣に雇用が確保されていることが前提となっています。
「経済センサス」によれば、市内の就労者数は30,420人となり、平成29年から令和3年までの5年間で約3,000名、約10%増加しました。要因の一つとして、京奈和自動車道の整備推進により、郡山ジャンクションから市内に繋がる「名阪側道」の周辺や、天理インター周辺で、産業立地が進んだことが挙げられます。本市都市計画マスタープランでは、この一体を「産業振興地区」と位置づけています。市街化調整区域における建蔽率等の制限等についても、奈良県と問題意識を共有し、規制緩和に向けた働きかけを行っています。今後は、農振法の改正により、農地転用許可の制限が強まることも見込まれますが、食糧安全保障と地方の活性化のバランスに配慮されるよう、県内市町村と連携しながら、国県への意見具申も続けます。
令和元年以降の立地件数は、概ね1㏊以上の大型土地利用に限っても、計画中を含めて15件に上りました。また、市内の宿泊室数は増加傾向にあり、平成30年の約5倍にあたる約600室となりました。こうした産業誘致と雇用数の増加を、市内の活力増進と市民の実感につなげることが重要です。誘致企業全般、特にサービス業及び製造業の企業では市内への事業所設置に係る新たな従業員の確保が課題となっており、本市雇用奨励金制度や奈良労働局と連携した面接会の開催など、積極的な支援も実施していきます。
道路ネットワークの整備では、都市計画道路 別所丹波市線の整備を令和7年度も進めます。また、南北の交通アクセスの軸となることが期待される「都市計画道路東井戸堂西長柄線 通称『九条バイパス』」は、奈良県が事業主体となり、路線の南側から工事が進められています。布留川南流付近では河川の付け替えが必要となり、令和6年度から橋梁下部・地盤改良工事が着手されています。本市としても、周辺の市道24号福知堂吉田線の整備など事業進捗が円滑になるよう連携協力して参ります。
物価高騰対策と市内消費の喚起では、デジタル地域通貨「イチカ」を活用した事業を進めます。令和6年に物価高騰対策のため配布したイチカは、約85%にあたる1億400万円分が市内加盟店で利用されました。今月からは、長引く物価高騰への更なる支援策として、市民一人あたり2,000円分のイチカ、中学生以下の市民には3,000円分を加えた計5,000円分のイチカを配布します。利用期限後の7月からは、イチカのポイント還元事業を実施予定です。昨年から開始したポイント還元事業では、チャージカードの利用額が月500万~600万円に大幅に増額しました。
イチカの活用は、こども食堂支援などの「イチカプラス」事業の他、体験型観光事業「おてつたび」や「生ごみ堆肥ワークショップ」への参加促進、妊産婦のための支援給付交付金の上乗せ、健康増進など様々な政策間連携が進んでいます。令和7年度は、SDGs未来都市としての本市取組みに、より幅広い市民が参加いただくためのツールとして、一層の利用促進を図ります。
市内の創業支援では、天理市商工会が国の特定創業支援事業の認定を受けています。商工会による創業スクールを受講した創業希望者に対して、創業時の登記費用や融資制度の優遇が受けられるよう市が認定を行います。令和6年度は、「天理市創業支援等事業計画」を更新し、令和12年度までの国の認定を受けることができました。これに基づき、商工会及び県よろず支援拠点等の関係団体と連携しながらスクールの運営を継続し、テレワークセンターやインキュベーション事業とも絡めた総合的な創業支援を実施します。
天理市商工会は、天理大学とも連携協定を締結し、大学生のインターンや地元就職の促進を目指しています。本市としても、この動きを最大限サポートするため、インターン参加者が実際に地元事業者に就職した場合、奨学金返済の補助なども検討していきます。大学生の地元就労支援は、中小企業家同友会なども重視しており、本市としても連携強化を図ります。
ふるさと納税の推進では、令和6年度の寄付額は昨年度に引き続き約1億3千万円を維持しており、大口の一般寄附を含めると約1億7千万円となる見込みです。しかしながら、ふるさと納税制度における自治体間の競争は年々激化しており、寄附額の維持及び拡大は大変厳しい状況となっています。ただし、本来の趣旨から逸脱したような返礼品の活用や、10月から廃止されるポイント付与などに依存しないことが重要です。
農産品等に加えて、古墳の麓に泊まれる宿としてメディア等で話題になっている萱生町のcofunia(コフニア)での宿泊及び体験型返礼品など、地方の活力を共に高めるような返礼品の開発に努めます。
企業版ふるさと応援寄附金は、本市が進める地方創生プロジェクトに共感くださった企業からお預かりしています。令和6年度は17社の企業様より合計6,014万円を超える寄附を賜りました。国際交流や文化・スポーツ事業など、本市単独の予算では実施が難しい事業を支えていただいており、令和7年度も協賛を得られる事業を積極的に発信し、さらなる寄附の獲得を目指します。
農業の振興では、令和6年に「オーガニックビレッジ宣言」を行った高原地域において、農林水産省の制度を活用し、令和7年度より農村型RMO(地域運営組織)の形成を目指します。これは、持続可能な農村コミュニティを地域住民自らが守り、農業の活性化とともに、観光振興、移住定住促進、住民の生活支援などを包括的に行うための枠組みです。
高原地域では、奈良県が進める「特定農業振興ゾーン」への認定に向けて申請します。これにより、地元負担がない形で圃場整備を行います。県との協議では、将来に渡って担い手を確保するために企業の参入を求められており、これまで「福住村プロジェクト」の趣旨に賛同してきた企業誘致を地元住民と進めます。福住村プロジェクトでは、有機農業を軸に、里山資源の活用による循環型社会の形成を目指しており、福住小中学校との連携も進んでいます。令和7年度は、広葉樹の活用に道を拓くことで、針広混交林化を育成するため、旧山田キャンプ場付近でモデル事業を行います。
特産品の開発事業では、刀根早生柿の販路拡大を進めており、大橋議長にも参加いただき沖縄への出荷が定着しています。令和6年度は、猛暑やカメムシの発生により収量が減少したものの、シンガポールや香港への試験的な出荷も行いました。令和7年度は一層の販路拡大を目指します。また、天理市集落営農組織連絡協議会で栽培されている特別栽培米を、前栽こども園の給食食材として導入しています。給食活用による地産地消は、今後も重要な手法と考えています。
また、地域農業の将来の在り方を示した「地域計画」が現在42地域で策定されています。
集約化や効率化に取り組む場合、国の補助金等を活用し、必要な農業用機械や施設の導入支援を行います。
若手農業者への支援では、令和6年度は4Hクラブが運営する「チャレンジファーム」において、大和スイカや赤いスイートコーン「大和ルージュ」の作付けを実施しました。令和7年度は、「大和スイカ」を始め新規作物に取り組み、ブランド力を持つ品種の選定と定着を目指します。新規就農者への支援も、令和6年度は計9名に実施しており、令和7年度は8名に実施予定です。
また、天理大学が農業生産法人「天理アグリ」を創設し、萱生町で刀根早生柿の普及や放棄地の解消などを目指しています。天理駅前広場コフフンで大学と実施している「天大フェスタ」での産品販売や、天理大学「i Connect ショップ」での販売、「天天カフェ」での活用など、大学との連携事業を通じて市もサポートしていきます。
観光と農業の連携では、萱生町で柿収穫の人手不足を解消しつつ、観光コンテンツとして開発するため「おてつたび」事業を進めています。令和7年度もリピーターの増加を図り、農業を通じた関係人口の創出に向けたきっかけづくりを行います。
鳥獣被害の防止対策では、防護柵の設置補助や捕獲活動の経費補助を行っています。ICTを活用した囲いわなも運用しています。令和6年度は繁殖期に合わせた集中捕獲を含め、2月末までに計690頭を捕獲しました。全国的に狩猟の人材不足が深刻化しており、狩猟免許の新規取得にかかる試験手数料や講習料の経費を引き続き補助します。
産官学連携による観光・文化スポーツの促進では、天理駅南団体待合所内を天理大学のサテライトキャンパスとして位置づけ、観光・農業を担う人材育成を令和6年度から開始しました。本件は、天大・モンベル共同体と連携して進めており、「学び」「実践」「ビジネス展開」を一体的に行う取組として「新しい地方経済・生活環境創生交付金(旧:デジタル田園都市国家構想交付金)」の対象事業にも採択されました。令和7年度は、大阪関西万博を契機としたインバウンド観光客への対応力を強化するため、位置情報(GPS)と連動した多言語音声ガイドの制作を予定しており、学生の参加により多様な視点を開発に活かします。
天理大学との連携では、スポーツツーリズムの推進も令和6年度に進みました。「ラグビースプリングカーニバル」の観戦ツアーでは、ラグビー部員によるガイドや解説を行い、柔道ツアーでは、穴井監督による柔道講話をお願いし、いずれも天理ならではの体験として好評を得ました。令和7年度は、ラグビーと柔道に加えて、男子バレーボール部の協力の下、ファンミーティングなども企画しています。
天理スポーツの選手応援やPRでは、天理大学のみならず小中高校生の多種多様な選手が全国・関西・近畿大会レベルの出場される際に、激励会や報告会を議会と合同で開催しています。春には、天理高校野球部がセンバツへの出場を予定しており、SNSを含めて市を挙げて応援できるよう発信に努めます。
プロスポーツとの連携では、サッカーJ3の奈良クラブとの間で包括連携協定を締結し、令和7年度も「天理市民デー」の開催を調整しています。また、プロバスケットボールチーム「バンビシャス奈良」によるバスケットクリニックを令和7年度も予定しています。同チームのパートナーであるロート製薬から企業版ふるさと納税による協賛を得ており、企業と連携したスポーツの振興を一層目指します。
令和13年に奈良県開催が予定されている第85回国民スポーツ大会・第30回全国障がい者スポーツ大会に向けて、本市はラグビー競技を御所市と共同で実施するために準備を進めています。市内の親里ラグビー場も老朽化が進んでおり、企業版ふるさと納税を活用した改修補助を検討して参ります。
マルシェや音楽イベントは、令和6年度はコロナ禍から回復して増加傾向です。コフフンでのイベント開催も、令和6年度は500件を超え、市政70周年記念の行事も続きました。令和7年度も、天理市PR大使の辻本美博氏が企画する「コフフンフェス」や、市内中学吹奏楽部が参加する「未来ステージ」、ダンスイベント「天理グッドフェローズ」などが準備されています。天理大学関係者を中心とした「ワールドフェスティバル」には、駐大阪のインドネシア総領事やインド総領事が参加し、関西を代表する国際交流イベントに成長しつつあります。「パフォーマンスフェスティバル」「天理の第九」や、銀杏並木を活かした「ほこてんり」など有志によるイベントも活発化し、令和6年度には「やまのべ・大和三山クラッシックカーフェス」など新たな企画も生まれました。令和7年度も、全日本ラリー選手権が本市を拠点に、県内では32年ぶりに企画されており、市としても支援して参ります。
「なら国際映画祭」との連携事業では、昨年に続いて本年も2月に若手監督を育成する「ナラティブJr.」の撮影が行われました。今回の短編作品「やまのべラジオ」は、本通り商店街を中心に市内各地でロケが行われ、市内商工関係者の皆様も多数出演いただき、9月の映画祭で上映される予定です。また、同映画祭を主催する河瀨直美監督は、大阪関西万博のパビリオンの一つでプロデューサーを務めています。これまで「ナラティブ」の枠組みで映画を制作した県内9市村と県が共同したイベントを、6月に万博会場で開催予定です。万博を契機に、なら国際映画祭との連携を一層深め、映像文化の力で本市の魅力をPRしていくことを目指します。
地域の産業を活かした観光振興では、「天理版オープンファクトリー2.0」を開始します。本市南六条町に物流拠点を新設した中川政七商店は、新潟県燕三条の「工場の祭典」や、越前地方の「RENEW」など、工芸分野でのオープンファクトリーを開拓してきた実績があります。これらの企画に携わったバイヤーの山田遊氏の参加も得て、市内事業者が持つ様々なノウハウや技術を、新しい観光コンテンツをして開発すること目指します。「新しい地方経済・生活環境創生交付金」の対象事業に採択されれば、令和7年度に実証事業を行う予定です。
新たな観光拠点としては、柳本駅舎に続いて、櫟本駅舎の利活用を令和7年度に進めます。昨年、有効活用の提案募集の結果、交渉権者を決定しました。JR西日本から譲渡を受けて宿泊施設として改修する予定です。鉄道ファンを中心に、泊まれる駅としてPRしていきます。
また、旧御経野共同浴場も、再活用を行う事業者を選定しました。令和7年末を目処に新たにサウナ施設も備えた「御谷温泉」としてリニューアルオープンする予定です。先行事例である御所町の施設のように、周辺地域全体の活性化に寄与することを期待しています。事業者に対しては、浴場運営の立ち上げ支援として3カ年に分けて助成を行います。
引き続き、民間活力と連携しながら、あるもの、まだ活用可能性があるものを活かした観光振興を目指します。
従来の拠点の中では、耐用年数を迎えつつあった市民会館が詳細調査の結果、鉄骨等の腐食状態までまだ60年ほどもつことが判明しました。音響をはじめ内部施設・備品の更新に数億円規模が今後必要になりますが、市民の文化芸術活動の拠点を守っていくために、包括的・効率的なリニューアル方法について、令和7年度に検討します。
全国的に書店がない自治体が増加し、経済産業省は「書店振興プロジェクトチーム」を発足させました。本市においても、読書文化を守るため、図書館と市内書店の連携を進めて参ります。
文化財の保存活用では、なら歴史芸術文化村と連携し、天理・桜井地域の文化財を紹介する「やまのべの文化財展」や、体験型ワークショップなどを本市文化財課が実施しています。最近では、大和古墳群のマバカ古墳の発掘調査などが注目されており、文化村周辺の文化財を活かした周遊観光も進めていきます。
観光以外の視点では、前の大戦末期に建設された「大和海軍航空隊大和基地(通称:「柳本飛行場」)の掩体の一部が私有地に遺されています。平和の尊さを後世に語り継ぐ遺構として一般公開するため、地元地権者の協力を得て整備することを目指して取組んで参ります。
第五の柱は、「人口減少社会に適応した持続可能な『行政サービス』の実現」です。
政府は、各自治体が行政サービスのために使用している自治体情報システムについて、原則、令和7年度末までに、住民情報システムのうち対象となる20業務を標準準拠システムへ移行するよう方針を示しています。本市は、令和6年11月に17業務の移行を目指していましたが、「標準仕様書の度重なる変更」や「定額減税等の大規模な制度改正」などにより、開発元ベンダーの作業が大幅に遅延しています。しかしながら、当初から時間的余裕をもって進めていたため、令和7年8月に生活保護システム、9月に住基、税、福祉の17業務のシステム、令和8年2月に戸籍・戸籍附票システムを移行する見込みであり、令和7年度中に20業務全て移行完了する予定です。
システム標準化により自治体運営の効率化、システム開発、運用コストの削減、データの連携、一元管理、住民の利便性向上などが図られるとされていますが、十分な効果を上げるためには、私共市役所自身が、主体性を持ってデジタル化を進めることが重要です。
標準化の完了を待つことなく実行可能なこととして、令和7年4月よりワンストップの「お悔やみコーナー」を設置します。身近な方が亡くなられた際、ご遺族による市役所での各種手続きの不安や負担を減らすため、専用ブースを市民課に設けます。完全予約制にしてご遺族が来庁されるまでに、故人に関連する手続きを必要な部署から事前におくやみコーナーに集約させておくことで、来庁時の申請書の記入や移動を要さずに手続きが完結できるようになり、手続き時間短縮と業務効率化を図ります。
当初は令和7年度の導入を目指していた「書かない窓口」「窓口DXSaaS」の導入は、標準化の完了時期の延期に合わせて、令和8年度にシステム導入をするべく準備を進めます。市民が来庁された際に、職員がタブレット等を用いて必要事項を聞き取り、その情報をデータ連携によって関連する部署へ繋げていくことが可能となります。
令和7年度は、窓口担当職員で構成される「窓口DXワーキンググループ」が中心となり、住民の利便性向上と業務の効率化を実現するための理想の窓口の実現に向けて、活発な議論と準備を進めます。
人口減少を見据えた持続可能な「行政サービス」の実現を目指し、生成AI技術やRPAなどのローコードツールを積極的に活用し、内部業務の効率化を図ります。
また、奈良県内の自治体で共同利用しているサービス「e古都なら」の電子申請サービスが令和7年末で終了予定です。次期サービスとして、奈良県が情報連携基盤として稼働させる「奈良スーパーアプリ」を活用し施設予約、電子申請を行います。同アプリは、防災分野での避難所運営支援や子育て分野において、生成AI導入による情報の効率的な提供が検討されており、本市としても積極的に活用して参ります。
DXを有効に使いこなすには、人材の育成が重要です。令和6年度に6名の若手職員を部署横断的に「DX推進リーダー」に任命し、育成を開始しました。令和7年度は、新たに6名を育成し、最新のデジタル技術やRPAなどの活用方法を習得させます。内閣府の地方創生人材支援制度を活用して民間企業から受け入れているICT推進専門官も継続して活躍いただきます。
マイナンバーカードは政府が「デジタル時代のパスポート」として利用促進に努めています。本市では、令和6年末時点で約8割の市民がマイナンバーカードを保有されています。マイナンバーカードの健康保険証利用を基本とするしくみに移行されたことから、高齢者等、移動が困難な方のために、行政書士会等とも連携し、施設や個人宅に訪問するなど細やかな申請支援を行い、「誰一人取り残さない、人に優しいデジタル市役所」を実現できるよう尽力しています。賛否もある中ですが、コンビニ交付を含めてカードの利用率も増えてきており、きめ細かい申請支援を継続します。
持続可能な行政サービスへの転換の締めくくりでは、例年の施政方針で10市町村によるゴミ処理広域化についてご説明してきました。新施設「やまとecoクリーンセンター」及び「やまとecoリサイクルセンター」は建設がついに完成し、本年1月7日に「やまとecoクリーンセンター」の「火入れ式」を行いました。可燃ゴミは1月20日から、リサイクル・不燃ゴミは2月から、実際に組合構成市町村より受け入れを開始し、現在は試運転を行っています。両施設の竣工式は4月24日を予定しており、4月末の竣工検査合格後、5月1日からの本格稼働を目指します。
4年間の環境影響評価を含めて、「山辺県北西部広域環境衛生組合の設立から9年、構想段階から10年がかりでした。今日まで組合事業を進めてこられましたのは、ひとえに櫟本校区・山の辺校区をはじめ地域住民の皆様のご理解、組合設立以来、組合議会をまとめて下さった大橋議長及び榎堀議員、本市議会の皆様のお力添えとご鞭撻、事務局長以下職員のみなさんの尽力の賜物と心から御礼申し上げます。
本組合事業は、10市町村による広域化という全国的にも先進的な、社会全体の環境負荷を低減する意義ある事業として、環境省、総務省はじめ政府から全面的な支援をいただきました。令和6年度は建設費用の高騰により約10億円の増額を急にお願いしたにもかかわらず、これを含め約86億円を全額交付いただき、市町村の財政負担を大きく軽減することができました。徹底した情報公開を含めて、誠心誠意業務に当たってきたことを評価下さったものと捉えています。
また、今回の広域化は西名阪自動車道・名阪国道、京奈和自動車道の道路アクセスなしには不可能でした。道路インフラが自治体の業務効率化に貢献した好事例として、国交省近畿整備局長のプレゼンなどにも紹介いただいています。
「やまとecoクリーンセンター」は、最新鋭の自動運転システムを備え、AIや遠隔操作により平時より少ない人員でも数ヶ月間稼働できるなど災害にも強い施設です。国内最高レベルの高効率を誇るエネルギー回収率の他、熱源を利用した温浴施設やフィットネスも併設しています。温浴施設はゴミを燃やす限り利用できますので、災害時に避難者の入浴に活用するなど防災拠点の役割を期待しています。環境学習施設や、プラント設備等をガラス越しに観ることができる見学通路を「やまとecoリサイクルセンター」を含めた両施設に整備しており、5月4日には、一般市民にお披露目するオープニングイベントを準備しています。
SDGs未来都市に認定された本市は、「プラスチックごみゼロ宣言」を行い、環境学習を「みんなの学校プロジェクト」の柱の一つとしてきました。「やまとecoリサイクルセンター」では、ゴミを利活用したサスティナブル・アートの作品がシンボルとして設置される予定で、これはアーティストと櫟本・山の辺小学校の児童が協力して制作したものです。環境学習施設では、サスティナブル・アートのワークショップなどを行うスペースを設けており、学校現場等と連携しながら、持続可能な社会に向けた啓発を行って参ります。
「やまとecoクリーンセンター」の稼働に合わせて、市業務として継続する収集作業及びごみの受入れ検査などは、「やまとecoリサイクルセンター」に隣接する「天理市清掃管理事務所」に移転します。1月末に工事は完了し、5月7日の運用開始に向け、移転の準備を進めています。新施設の建設に先立ち、周辺道路の混雑を緩和するため、ごみの持込は事前予約制を導入することをお約束していました。電話に加えて、インターネットを利用した24時間受付可能なシステムを導入することで、利便性の向上を図ります。5月7日からの運用開始に向け、4月16日から電話、インターネットにて受付を開始します。旧施設は5月6日まで従来通り運営しますが、新施設の運用開始当初は予約の混雑が予想されるため、移行直前の3月からゴールデンウイークにかけて、土曜・祝日の全日を臨時開場し、ごみの受入れを行います。
広域化は、旧施設を解体するまでを含めて広域化です。県内の旧い7施設を統合した組合事業では、旧施設の円滑な解体に向けた財政措置も政府に要望しています。現クリーンセンターの解体には30億規模の予算が必要と見込まれ、今後の本市財政にとって非常に重い負担となります。これまで、解体のうち補助対象外部分については起債償還時の交付税措置がなく、全てが自治体負担でした。本市は、広域化など旧施設が集約化される場合、解体について市単独事業分についても「公共施設等適正管理推進事業債」の活用による交付税措置を要望してきました。このほど、事務組合等による集約についても制度を活用できる道が拓けました。今後、確実に適用されるよう働きかけを継続して参りますが、実現すれば解体費用の約36%が交付税措置を受けられることになり、本市にとって大きな負担軽減になります。広域化の効果は、実に様々な点に及びます。
令和6年11月に奈良県広域水道企業団が発足し、令和7年度より事業を開始します。広域消防に続いて、大規模な広域化に本市は参画することになります。水道も消防も、安全・安心な市民生活を支える重要な自治体業務であり、これまで本市は制度設計から積極的に議論に加わり、公平公正な負担や料金設定、意思決定への市町村の参画と透明性の確保などに努めて参りました。これから、市単独で運営する火葬場なども2カ年の大規模修繕が必要な中、周辺自治体と協力できる点は協力し、政府や県からの垂直補完も引き出しつつ、運営や施設更新を合理化・効率化していくことは不可欠です。
多様なパートナーと協力しながら、市行政が自らなすべきことを明確にし、集中する。その際に、縦割りやその場限りの負担感で視野を狭めるのではなく、常にチームワークの中で動くことを意識し、柔軟に対応していく。デジタル化だけでなく、人口減少社会に適応した持続可能な「行政サービス」を実現するために必須の心構えとして参ります。
以上、令和7年度の主要な施策についてご説明しました。いずれも、天理市が人口減少社会にしなやかに適応しつつ、次の10年に向けて、天理らしい豊かさを育み、いつまでも住み慣れた地域で安心して暮らしていけるまちづくりのために必要な布石と捉えています。天理市から、持続可能な地方自治体のモデルを示していく志で取組んで参ります。慎重なご審議の上、ご承認を賜りますよう心からお願い申し上げます。
(以上)
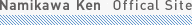
 ホーム
ホーム 政策・ニュース
政策・ニュース プロフィール
プロフィール なみかわ健後援会
なみかわ健後援会