天理市議会の12月定例会において、鈴木議員より来年10月に見込まれる市長選への出馬意向を質問いただき、これまでの11年間の総括と次の4年間の市政に掛ける思いをお答えしました。
不確実性を増している昨今、今年70周年を迎えた天理市も、この11年間で様々な試練に晒されてきました。以前の天理市は、人口を遥かに上回る来訪者を前提に町が形づくられ、多額の寄付金によって財政力を超えた規模の都市整備やきめ細かい行政サービスが支えられていました。
これまでの恩恵に感謝しつつ、他方で、市が土台から大きく変化していることを、正面から見据えざるを得ませんでした(※教育や福祉、文化やスポーツなどでの協働を、一層大切にしていくべきと考えて取組んでいます)。
しかし、逆境の中にあっても、天理市政はこの間、下記のように力強い歩みを続け、コロナなどの危機にも正面から対応してきました。
しかも市の貯金に当たる財政調整基金は、10億円を切りそうになっていたところから、今年度末の残高33億円の見込みで約3倍増。借金が財政を圧迫する度合いを示す将来負担比率は、101.9%から24.8%に1/4に大幅に減少しました。
必死にやりくりしつつ、ここまでやって来られたのは、決して私ひとりの実績ではなく、市議会と行政が「車の両輪」となり、市民の皆さまと三位一体で取組んできた成果、市職員の皆さんも一所懸命に尽力下さった賜物です。
*****
11年間の主な取組みを挙げます。
私の就任時、小中学校の耐震化が大きな課題でしたが、前栽小に続いて南中・北中を建替えて、耐震率100%を達成しました。エアコンも普通教室と特別教室に設置し(体育館は来年度に予定)、タブレット活用をはじめ教育のデジタル化も進めてきました。
市立幼保の再編とこども園化、私立保育所の新設等により待機児童を解消し、盆地部のどこかには受け皿がある状況を保っています。病児病後児保育を新設し、学童保育も学校校舎を活用することで、これまで待機児童を出さずに、預かり規模を500名から950名に拡大しました。
こどもの医療費助成を拡大し、高校まで現物給付化、未就学児の窓口負担を無償化した他、第二子以降の保育料の無償化、私立保育士の処遇改善も実施しました。
こども食童など食事を通じた居場所づくり、フードバンクとの連携等も進んでいます。
高齢者福祉では、住み慣れた地域で安心して暮らすことを最優先にして、生活支援コーディネーターを各包括支援センターの圏域に配置しました。地域密着型の介護を重視し、小学校区レベルで小規模多機能型居宅介護施設を整備しました。サロンなど居場所づくり、活脳教室などの認知症対策、健康づくりを進めてきました。
障がい者福祉では、手話言語条例の制定など、障がいの有無に関わらず支え合う町づくりを進めてきました。
「交通弱者」への支援では、移動販売が根付いてきた他、AIを活用した乗り合い交通サービス「チョイソコ」も今年度より開始しました。
市内の雇用創出では、名阪と京奈和沿線を中心に産業振興地区をマスタープランで設定し、企業立地支援や、シャープとの連携などを進めました。直近の経済センサスによれば、市内従業者数は5年間で約3,000名増加しました。ホテルの新設が続き、市内の宿泊客室数は約5倍に増加しました。
農業分野では高原を中心に有機農業の取組みを進め、「オーガニックビレッジ宣言」を行い、「SDGs未来都市」に認定されました。
「あるものを活かす」という発想は防災分野でも重視し、農業利水用のため池だった庵治池88,000立方メートルを治水利用に転換し、貯水量当たりの単価は、一般的な地下貯留槽の約1/100に抑えることができました。
大規模災害時には、避難所となる各学校において、体育館よりも居住性の高い教室を優先的に活用する計画を立て、トイレトレーラーも発注し間もなく配備予定です。
周辺自治体との連携では、ゴミ処理の10市町村での広域化を進めてきました。
老朽化した7つの施設を環境負荷の低い1施設に統合する取組みは、環境省はもちろん総務省や財務省からも高く評価されて全面的な支援を受け、ついに年末に建設が完了します。
地域の皆さまのご理解とご協力のお陰をもって、年明けから試運転、4月末に正式稼働の運びとなりました。
この他、天理駅前広場コフフンの整備、天理大学等との連携、デジタル地域通貨「イチカ」の導入など様々取組んできました(今回は、これまでFBなどで十分取り上げきれなかった生活密着のものを主に挙げました)。オール天理で力を合わせれば、今後の課題についても果敢に取り組んでいけると私は確信しています。
*****
他方で、今や国内の日本人人口は年間80万人を超えて減少し、今年の出生者数は70万人を下回る見込みです。「まち・ひと・しごと創生法」が施行されて10年が経ったものの、我が国全体で人口減に歯止めをかける社会システムの構築よりも、近隣自治体との住民の奪い合いに終始してしまったと、人口戦略会議の関係者も認めています。
国全体で少子化の原因となる課題に向き合い、無償化や補助金の給付に偏った自治体間の競争から脱却する必要があります。
しかしながら、地方における生産年齢人口が、直ちに反転することは容易には見込めません。
人口の流出を緩やかにする努力を続けつつ、本市が「人口減少社会適応都市宣言」で述べたように、人口減を現実の事象として認めながら、しなやか且つ持続可能な市民サービスへの転換、あるものを活かした天理らしい豊かさの創出を進めることが不可欠です。
その具体策として、天理市は地域の学校を「みんなの学校=地域連携型小規模校」としてできるだけ守っていく方針を示しました。こども達を地域全体で育み、それを通じて、多世代が支え合う地域のコミュニティも育む「共育(きょういく)」を掲げています。
今後20年間に、学校や公民館など大半の公共施設が耐用年数を迎える中、施設の総量を合理化しながら、市民サービスを守り、かつ充実させていくことは大きなチャレンジです。
従来の使用方法に捉われることなく、新たな付加価値を生み出す複合化が避けられません。「みんなの学校」への転換は、その中核と位置付けています。
また、能登半島地震をはじめ、自然災害が続いています。来年は阪神淡路大震災から30年目となる年です。避難所となる学校を、平時から地域の絆づくりの拠点と位置付けることは、共助と公助の力で、救える命を救うことに繋がります。
教員不足が全国的に課題となる中、先生方が子ども達に向き合うことに集中できる環境が必要です。「みんなの学校」を実現していくために、本市は「学校三部制」を打ち出しました。
責任の所在や分担を明確化する一方で、学校教育と社会教育、生涯教育が相互に高め合うことを目指します。経済的な格差によって、子ども達の体験機会にも大きな格差が顕在化しています。
諸先輩が地域で育んできた絆の中で、多くの人たちと学ぶチャンスを作ることは、貧困の連鎖を和らげ、天理らしい豊かな教育を実現する施策と捉えています。
そして私達は今、真に「こどもまんなか」の教育保育への転換を、天理から全国に広めていく志を以て取り組んでいます。
今年度に開設した「ほっとステーション」は、市全体で教育・保育現場を支え、心理士などの専門家の視点を交えながら、誰もが安心できる学校・園・所をつくる事業として、文部科学省や全国の自治体から注目を集めています。
総合教育会議では、ほっとステーションを通じて改めて見えてきた現状を基に、令和7年度から5年間を対象に、新教育大綱を議論しています。「集団指導から、ひとりひとりの『しなやかさ』を育む『共育』へ」をテーマ案として掲げ、社会が必要な「人材」を製造する視点を転換し、次の時代を生きる人間が、幸せに生きていくための力を共に育むことを目指しています。
私は、終生市長職に留まる訳にはもちろんいかないと思いますが、この3期目の間に、このテーマを自分の人生の使命と思い定めることができました。ライフワークとして取り組んでいく所存です。
次の4年間に何としても確かな道筋を、志を同じくする皆さんと拓いていきたいと考えています。
これに加えて、家庭の抱える課題が多様化、複雑化する中、福祉の分野においても縦割りの対応では全く追いつかない状況です。教育と福祉の連携も不可欠です。社会福祉協議会の充実を含めて、重層的な支援体制の構築を急いで参ります。
町の活力を高めるために、歴史、文化芸術、スポーツなどの天理の「宝」をこれまで以上に活かすことも大切です。天理大学や民間団体、企業との連携を深め、地域と共に新たな価値を生む努力を続けます。
まだ数十年間の利用が可能と判明した市民会館なども、従来どおりの使用であっても数億円の追加投資が必要です。それに見合う活用の促進を図ります。
雇用のさらなる創出と県内の道路整備の促進、とりわけ京奈和自動車道の早期開通はパッケージと捉えています。県と市町村が一体となった要望に引き続き積極的に貢献しながら、産業振興地区を中心にいっそうの企業立地、既存事業者の定着と活性化を図ります。
頻発する自然災害の対応では、災害対応の体制を全庁的に見直しています。救える命を救う、災害関連死を一人でも少なくすることを目標として、避難生活を支える物資の受領、管理、運搬など市内の運送倉庫業との具体的な連携なども検討を加速化します。
デジタル化が進む中、市民サービスを支える市役所も生まれ変わらなければなりません。限られた人員と予算、時間をもって、できるだけきめ細かい市民サービスを、やりがいを持って進められる市役所への転換です。
一年後ろ倒しとなりましたが、政府が進める基幹業務システムの統一・標準化を令和7年度に着実に実施し、令和8年度には「書かない窓口」窓口DXSaaSをはじめとして、抜本的な合理化と効率化、働き方改革の実現を図ります。
これらの施策を進めていくため、市民の皆様のご信任を得て次の4年間の市政をお任せいただけるよう、先ずは来年10月までの任期を全力で努めて参ります。令和7年度予算案は、本格予算として議会に上程できるよう取り組む考えであり、引き続き議員各位のご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。
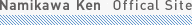
 ホーム
ホーム 政策・ニュース
政策・ニュース プロフィール
プロフィール なみかわ健後援会
なみかわ健後援会